�@ �m�I���Y�헪�{���́A�u ����I�ȃ��m�̋������s�����������20���I�^�̍H�ƃ��f���̎��ォ��A�̌��⋤�������߂郆�[�U�̑��l�ȉ��l�ς��s����������鎞��ւƕω����钆�A�s�����������͂̌���ƂȂ閳�`���Y���ʂ��������͑��債�Ă���v�Ƃ��āA�u �m���̃r�W�l�X���l�]�������^�X�N�t�H�[�X�v���J�ÁB���̌��ʂ��u���̃r�W�l�X���l�]�������^�X�N�t�H�[�X���`�o�c���f�U�C������`�v�Ƃ��Ĕ��\�B���̃y�[�W�ɂ́A�����̓��e���Q�S��ɕ����Čf�ڂ���B�P�P�^�Q�S
��Q�́@���l�n�����J�j�Y���̔c���ƃf�U�C��-6
��R�� �m���헪�͑S�ЁE���ƂƂ̊W�ɂ����č���
�{�߂ł́A�r�W�l�X���f�����x����o�c�����Ƃ��Ă̒m���̐헪�ɂ��Đ�������B��P�͂P�߂ŐG�ꂽ�悤�ɁA21 ���I�^���f���̉��ł́A�m���́A�o�c�����̈ꕔ�Ƃ��Ċ�Ɩ��͎��Ƃ̉��l�n�����J�j�Y���̒��Ŋ��p����邱�Ƃ����߂���B���������āA��Ɩ��͎��Ƃ̉��l�n�����J�j�Y���ɓK������悤�ɁA�m���̑n�o�A���B�A���p���͓]�p���̐헪�����肷�邱�Ƃ��K�v�ł���B�܂��A���̋t�ɁA���Ж��͑��ҁi��w�E�����@�֓����܂ށj���ۗL�E���p����m���̏�ɓK������悤�ɁA��Ɩ��͎��Ƃ̉��l�n�����J�j�Y�����f�U�C�����邱�Ƃ��K�v�ł���B�ߔN�ł́A�m���̏�ɁA����Ɏs��̏���������āA��Ɩ��͎��Ƃ̉��l�n�����J�j�Y�����f�U�C�����鎎�݁i�uIP�����h�X�P�[�v�v�Ə̂����B�j�����ڂ���Ă���B
�@�{�͑�P�ߋy�ё�Q�߂ł́A��Ɩ��͎��Ƃ̉��l�n�����J�j�Y�����f�U�C��������@�ɂ��Ĉ������B�{�߂ł́A�m���헪�����肷����@�ɂ��Ĉ����B
�m���͕����̎��ƂɌׂ��Ďg�p���邱�Ƃ��\�Ȏ����ł��邽�߁A�S�ЁE���Ɛ헪�ƊO�����܂��A�S�Ѓ��x���E���ƃ��x���̗����_����m���̊m�ہE�����E���p�̐헪�����肷�邱�Ƃ��]�܂����B���Ǝ��_�ł́A�����̃r�W�l�X���f���ɂ����Ēm�����ǂ̂悤�Ɋ��p���邩�A�����̃r�W�l�X���f�����x����m�����ǂ̂悤�Ɋm�ہE�������邩����������B�S�Ў��_�ł́A�ۗL����m�����o�c�ōő�����p���邱�Ƃ�ڎw���A��̎��Ƃ̒m�������̎��ƂɊ��p�E�]�p�\�ł��邩�݂̂Ȃ炸�A��Ƃ̐����͂̌����G�R�V�X�e���̌`���ɒm���������Ɋ��p���邩������������B�ȉ��ł́A�m���|�[�g�t�H���I���}�l�W�����g���邱�Ƃɂ��m���̊m�ہE�����Ɍ������헪�̍���ɂ��Đ������A����ɁA�I�[�v�����E�N���[�Y�����ӎ������m���̊��p�헪�̍���ɂ��Ă���������B
��P�� �m���|�[�g�t�H���I���}�l�W�����g
�m���헪�̍���ɂ������ẮA���Ђ⑼�Ђ��ۗL����m���̑S�̑��₻���̑��݊W��c�����邱�Ƃ�ʂ��āA���Ђ��m�ہE�������ׂ��m���i�Z�p���j�ƁA�������ׂ��m���i�Z�p���j�ʂ��邱�Ƃ����߂��Ă���B�ȉ��A��̓I�ȕ��@�ɂ��Đ�������B
�i�@�j���ЁE���Ђ̒m���|�[�g�t�H���I�̕��͂�ʂ����m���헪�̍���
���ЁE���Ђ̒m���|�[�g�t�H���I�̕��͂ł́A���Ђ̌���A���Ђ̓����A���ЂƑ��Ђ̊W���i���ЂƋ������ЂƂ̃p���[�o�����X���j�͂���B���̍ہA�Y�ƕ�����ĐV�������l�ݏo���`�����X�̔F���ƁA�ٕ��삩��̎Q���̋��Ђւ̑Ή��Ƃ����ϓ_����A���݂̋����݂̂Ȃ炸�A���L���e�Ђ̓�����c�����邱�Ƃ��d�v�ł���B
���ЁE���Ђ̒m���|�[�g�t�H���I�̂����A���ɁA���ЂƑ��ЂƂ̋Z�p�̊W����c��������@�Ƃ��āA�������Ɋ�Â��Z�p��������Ղ�����@���m���Ă���B�Z�p��������Ղ��邱�ƂŁA���ЁE���Ђ̋��݂��݁A�Z�p�̂ǂ��Ɍ������邩��c��������A�V���ȋ����̏o����\��������A�r�W�l�X�p�[�g�i�[�̔����Ɋ��p�����肷�邱�Ƃ��ł���B
�܂��A�Z�p�����̘��Ղ́A�l���`�������ۂ̃V�i�W�[���ʂ̗\���ɂ����p���邱�Ƃ��ł���B�Ⴆ�A���삪���S�ɏd�Ȃ��Ă���ꍇ�̓V�i�W�[���ʂ�����\�����Ⴂ�̂ɑ��A���삪������x�d�����Ă��邪�d�Ȃ��Ă��Ȃ��̈悪��r�I�����ꍇ�́A���݂��̋��݂������Ƃ��ł��A�V�i�W�[���ʂ�����\���������ƍl������B
���ЁE���Ђ̒m���|�[�g�t�H���I�̕��͂Ɋ�Â��A�S�А헪�E���Ɛ헪�܂��Ăǂ̂悤�Ȓm�����m�ہE�������ׂ����A�܂��A�m�ہE�������ׂ��m�����A���Ђőn�o���邩�A���҂���l�����邩�ɂ��Ă��������邱�Ƃ��d�v�ł���B
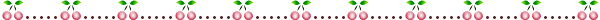
 2025�`2030�N��������������V���Ȓm�I���Y�헪�r�W����
2025�`2030�N��������������V���Ȓm�I���Y�헪�r�W����

 �m�I���Y���i�v��2020
�m�I���Y���i�v��2020

 �m���̃r�W�l�X���l�]�������^�X�N�t�H�[�X���`�o�c���f�U�C������`
�m���̃r�W�l�X���l�]�������^�X�N�t�H�[�X���`�o�c���f�U�C������`

 �����N�W
�����N�W WIPO
WIPO ������
������ �o�ώY�Ə�
�o�ώY�Ə� �ō��ٔ���
�ō��ٔ��� �m�I���Y�헪�{��
�m�I���Y�헪�{�� ������
������ �A�����~���
�A�����~��� ���كZ���^�[
���كZ���^�[
